
京都市で事業を営んでいる方なら、日々出るごみの処理について疑問を感じたことがあるのではないでしょうか。「家庭ごみとして出せば安く済むのでは?」「なぜ事業ごみは特別な処理が必要なの?」といった疑問をお持ちの事業者も多いことでしょう。
実は、京都市ではごみの性質と排出者の責任によって「家庭ごみ」と「事業ごみ」を明確に区分しており、それぞれ異なるルールと料金体系が適用されています。誤った処理を行うと法的な問題に発展する可能性もあるため、正しい知識を身につけることが重要です。
この記事では、京都市における事業ごみと家庭ごみの違いについて、分別方法から料金体系まで詳しく解説していきます。2025年の料金改定情報も含めて、事業者が知っておくべき最新情報をお届けします。
目次

京都市では、ごみの性質と排出者の責任によって「家庭ごみ」と「事業ごみ」を明確に区分しています。この区分は単純に「どこから出たか」だけでなく、廃棄物処理法に基づく法的な責任の違いにも関わっています。
家庭ごみは、一般家庭の日常生活から生じる一般廃棄物で、京都市が定める分別区分に従えば市の収集サービスを利用できます。市民は有料指定袋を購入することで処理手数料を支払い、決められた収集日に地域の集積所に出すだけで回収してもらえます。
一方、事業ごみは、商店・事務所・工場等の事業活動から発生する廃棄物で、さらに「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。京都市では事業ごみの定期収集は行っておらず、排出事業者が自らの責任で処理することが法律で義務付けられています。
事業者は透明または白色透明袋を使用してごみを分別し、京都市が許可した一般廃棄物収集運搬業者に委託するか、自らクリーンセンターへ搬入する必要があります。この自己責任の原則が、家庭ごみとの最も大きな違いといえるでしょう。
参考:事業ごみとは(京都市)
「事業ごみを家庭ごみの指定袋に入れて出せば安く済むのでは?」と考える事業者もいらっしゃるかもしれませんが、これは絶対に避けるべき行為です。その理由と深刻な影響について詳しく解説します。
まず最も重要な点として、事業者が家庭ごみの収集場所に事業系ごみを出すことは、廃棄物処理法第16条における「不法投棄」に該当する法令違反行為です。この違反には極めて厳しい罰則が科せられており、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)等の対象となります。
また、仮に黄色の指定袋や燃やすごみ用袋に事業ごみを入れても、京都市では収集を行いません。事業系ごみの袋には市指定袋を使用できないため、必ず透明または白色透明袋で中身が確認できるようにして、適切な処理ルートで処分する必要があります。
さらに深刻なのは、不適正な処理が発覚した場合の経済的損失です。罰金だけでなく、適正処理のための追加費用、行政処分による営業への影響、社会的信用を失うなど、さまざまな経済的損失を被る可能性があります。
想定される損失パターン
廃棄物処理法違反による不適正処理が発覚した場合、以下のような深刻な影響が想定されます。
廃棄物処理法では、法人の場合最大3億円以下の罰金が科される可能性があります。また、月数万円の処理費用を節約しようとした結果、事業存続に関わる重大な損失を被るリスクがあることは、多くの専門家が指摘するところです。
特に飲食業では食品衛生への信頼が事業の根幹であるため、廃棄物処理の不備が営業許可にも影響し、事業継続そのものが困難になる可能性があります。
短期的なコスト削減を狙った結果、事業存続に関わる重大なリスクを招く可能性があることを十分理解しておきましょう。

京都市における家庭ごみと事業ごみでは、分別の基準や方法が大きく異なります。特にプラスチック類の扱いには注意が必要です。
| 項目 | 家庭ごみ | 事業ごみ |
|---|---|---|
| 使用袋 | 京都市指定袋(有料・色分け) | 透明または白色透明袋のみ |
| プラスチック類 | 資源ごみ(週1回収集) | 産業廃棄物(専門業者委託必須) |
| 分別基準 | 市民向け8種類区分 | 一般廃棄物・産業廃棄物の2分類 |
| 責任者 | 市が収集・処理 | 排出事業者が全責任 |
京都市の家庭ごみは、有料指定袋制により4分別・8種類以上に区分され、それぞれ決められた収集日があります。すべての分別基準は以下の通りです。
事業者は一般廃棄物と産業廃棄物を自ら分別し、透明または白色透明袋で排出する必要があります。事業系ごみの分別基準は家庭ごみよりも厳格で、特にプラスチック類の扱いが大きく異なります。
| 分類 | 扱い | 主な品目例 | 処理方法 |
|---|---|---|---|
| 紙類 | 事業系一般廃棄物 | コピー用紙、事務書類、新聞、段ボール | 許可業者に委託またはリサイクル |
| 缶・びん・ペットボトル | 事業系一般廃棄物 | 飲料缶、びん、ペットボトル | 許可業者に委託 |
| プラスチック類 | 産業廃棄物 | すべてのプラスチック製品・容器 | 産業廃棄物処理業者に委託 |
| 金属・ガラス・陶器 | 産業廃棄物 | オフィス家具、金属部品、陶器 | 産業廃棄物処理業者に委託 |
| 家電・機械類 | 産業廃棄物 | PC、プリンタ、電子機器 | 専門業者に委託 |
最も注意すべき点は、家庭では資源ごみとして扱われるプラスチック類が、事業所から出る場合はすべて産業廃棄物になることです。プラスチック製の弁当容器、ビニール袋、発泡スチロール等は、事業者が出す場合は産業廃棄物処理業者への委託が必要になります。

家庭ごみと事業ごみでは、収集方法にも大きな違いがあります。
| 項目 | 家庭ごみ | 事業ごみ |
|---|---|---|
| 定期収集 | あり(市が実施) | なし(市は収集しない) |
| 収集頻度 | 燃やすごみ週2回、資源ごみ週1回等 | 業者との契約による |
| 収集場所 | 地域の集積所 | 事業所前または指定場所 |
| 予約 | 大型ごみのみ必要 | クリーンセンター搬入時必須 |
| 処理業者 | 京都市 | 許可業者への委託が義務 |
| 緊急対応 | 収集日まで待機 | 契約業者と調整可能 |
京都市の家庭ごみは、有料指定袋制により以下のスケジュールで定期収集されます。
| ごみの種類 | 収集頻度 | 使用袋 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 燃やすごみ | 週2回 | 黄色半透明袋 | 水分をよく切る |
| 缶・びん・ペットボトル | 週1回 | 無色透明資源袋 | 中身を空にしてすすぐ |
| プラスチック類 | 週1回 | 無色透明資源袋 | 軽く洗って汚れを落とす |
| 小型金属類・スプレー缶 | 月1回 | 透明袋に「金属」表示 | スプレー缶は使い切る |
一辺30cmを超える家具・家電は予約制で収集します。電話またはインターネットで事前予約を行い、400円券を購入して品目ごとに必要枚数を貼り付け、指定日の朝に出します。
大量のごみや引越しごみを自らクリーンセンターに持ち込む場合は、搬入日前日までにインターネットや電話で予約が必要です。
京都市では事業系ごみの定期収集は一切行いません。これは廃棄物処理法により、事業者自らが処理することが義務付けられているためです。
事業系一般廃棄物は、京都市が許可した一般廃棄物収集運搬業者と契約して収集してもらう必要があります。業者選定時は以下の点を確認しましょう。
プラスチック類や金属くず、ガラスくずなどの産業廃棄物は、一般廃棄物とは別の許可を持つ産業廃棄物処理業者に委託する必要があります。
もし、事業者が自らごみをクリーンセンターに持ち込む場合は、搬入日前日までに予約が必要です。2024年10月から事前予約制が導入され、インターネットまたは電話での予約が必須となりました。
マンション等で民間業者が家庭ごみを収集する場合は、透明袋を使用し、缶・びん・ペットボトルやプラスチック類もビルのルールに従って出します。この場合、市の指定袋は使用しません。

家庭ごみと事業ごみでは、料金の仕組みが根本的に異なります。
| 項目 | 家庭ごみ | 事業ごみ |
|---|---|---|
| 支払い方法 | 指定袋購入 | 業者への月額料金 |
| 料金設定 | 市が統一価格で設定 | 業者ごとに料金が異なる |
| 基本的な負担 | 45L袋45円〜 | 月額5,000〜20,000円程度 |
| 大型ごみ | 400円券(定額) | 別途見積もり |
| 処理手数料 | 10円/kg(直接搬入時) | 15円/kg(2025年4月改定後) |
| 産業廃棄物 | 該当なし | 別途産廃業者料金 |
家庭ごみの処理手数料は、指定袋の購入費として支払います。1枚あたりの価格は以下の通りです。
| 袋の種類 | 容量 | 価格(1枚) |
|---|---|---|
| 燃やすごみ用(黄色半透明) | 45L | 45円 |
| 30L | 30円 | |
| 20L | 20円 | |
| 10L | 10円 | |
| 5L | 5円 | |
| 資源ごみ用(無色透明) | 45L | 22円 |
| 30L | 15円 | |
| 20L | 10円 | |
| 10L | 5円 |
その他の料金
事業者は許可業者との契約により、収集運搬料金と京都市のごみ搬入手数料を支払います。京都市は排出事業者責任とごみ減量の観点から、2025年4月1日にごみ搬入手数料を改定しました。
| 項目 | 現行(2024年) | 改定後(2025年4月~) |
|---|---|---|
| 課金単位 | 100kg単位 | 10kg単位 |
| 料金 | 1,000円/100kg | 150円/10kgまで(約15円/kg) |
| 特例 | なし | マンション等プラスチック類:75円/10kgまで |
この改定により、少量排出事業者の負担軽減と、より細かな単位での課金が実現されます。
産業廃棄物は廃棄物の種類(廃油、廃酸、金属くず等)により処理料金が異なり、民間業者の提示額に基づいて処理されます。一般廃棄物処理料金とは別体系で、市の指定袋は使用できません。
また、事業者が直接クリーンセンターに搬入する場合の手数料は、家庭と同じく100kg以下1,500円、100kg超は10kgごとに200円加算です。搬入前日までの予約が必要で、搬入時に車両を計量して精算機で支払います。
支払い方法
参考:令和7年4月1日から『ごみ搬入手数料』を改定します!(京都市)
事業ごみの適正処理について理解を深めた結果、「やはり信頼できる許可業者に委託したい」とお考えの事業者様も多いのではないでしょうか。
「ごみの窓口」では、京都市発行の一般廃棄物収集運搬許可証を保有し、伏見区をはじめとする京都市内の事業者様に対して、安心・安全なごみ処理サービスを提供しています。
事業ごみの処理でお困りの方、現在の業者からの切り替えをご検討の方は、ぜひ「ごみの窓口」にご相談ください。無料見積もりで最適なプランをご提案し、スムーズな業者切り替えをサポートいたします。
お気軽にお電話やLINE、お問い合わせフォームからご連絡ください。
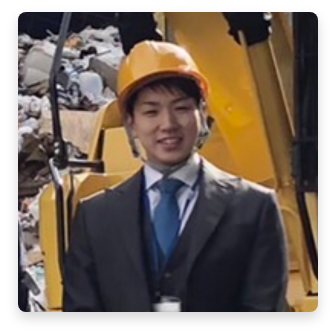
山本 智也代表取締役
資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。 不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。